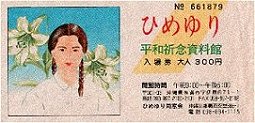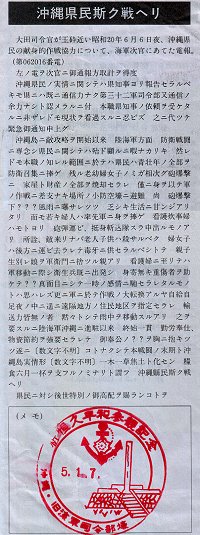血戦の地
|
本島南部。私の生まれた年…昭和42年からたった22年前に、大きな戦いの遭った地。もうすぐ50年が経とうとしている今(平成5年)も、戦争の跡はあちこちに残っていた。私が見たその跡は、すべて地面の下にあった。 |
|
旧海軍司令部壕は中に入ることができた。大人が立って歩ける程度の大きさのトンネル、と言えばわかりやすいだろうか。そのトンネルでつながれた各部屋は、必要最小限の大きさしか無い。それでもここはまだ「壕」と呼べるものだった。後に訪れた2カ所に比べれば。 「ガマ」と呼ばれる石灰質の洞穴が、沖縄本島にはたくさんある。大型爆弾の直撃にも耐えうる頑丈なこれらのガマに、日本軍は立て籠もった。多くの避難民も、ガマに逃げ込んだ。陸軍病院壕と旧陸軍第32軍司令部壕は、それぞれその中のひとつ。昭和20年5月下旬、消耗を重ねた日本軍は喜屋武半島へ撤退。南風原にあった陸軍病院は伊原に、首里にあった第32軍司令部は摩文仁へ落ち延びた。
↑ひめゆり平和祈念資料館のチケット。 旧海軍司令部壕入場者用パンフの裏表紙。→ |
|
| 通称「摩文仁の丘」と呼ばれる平和祈念公園は、供養塔と墓碑が点在する広い「霊園」だった。その南端、海に面した崖の中腹に旧陸軍第32軍司令部として使われたガマがある。入口部分は陸軍病院のガマよりさらに狭い横穴。崩落の危険があるために中には入れない。入口から見た限り、とても「壕」とは呼べない…まさしく「追いつめられた場所」だ。ここで、司令官・牛島満中将と参謀長・長勇中将が割腹自決した。
私が実際に目にした戦争の跡は、これだけ。 私は「自衛隊は必要である」と考えている。昔から、そして今も。この沖縄で感じた事を、もちろん踏まえた上でなお、世界が一斉に軍備を放棄しない限り自衛隊は必要だと考える。ただ、有事の時に沖縄戦のような「避難民を巻き込んだ悲惨な戦闘」があり得る事を、ここ沖縄で改めて再認識した。 |